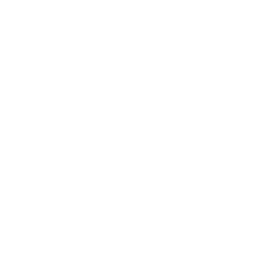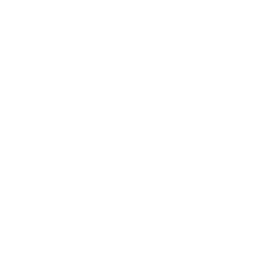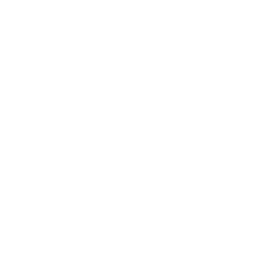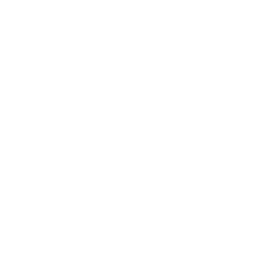非認知能力の伸ばし方!子どもの能力の向上で避けることもご紹介

近年の子どもの教育には「非認知能力の向上」が大切だといわれています。しかし能力を伸ばすには何をすれば良いか、具体的な方法がわからない人もいるでしょう。そこでこの記事では、非認知能力を伸ばす方法や、能力の向上で避けることを解説します。
この記事を読むための時間:3分
目次
非認知能力について
非認知能力とは、判断力や思考力、コミュニケーションスキル、対応力などの数値化できない能力のことです。学力や運動能力のように測定して数字で表すことはできませんが、子どもが社会で生きていくためには必要な能力になります。向上すると豊かな人格を形成できるようになり、将来の選択肢を広げることから、近年の子育てではとても注目されています。
子どもの非認知能力の伸ばし方
子どもの非認知能力の伸ばし方を、4つご紹介します。
- 子どもの挑戦を肯定する
- 判断は子どもにさせる
- 失敗を経験させる
- 頑張りを褒める
子どもの挑戦を肯定する
非認知能力を伸ばすには、子どもの挑戦を肯定しましょう。子どもはやりたいことがあっても、親や大人に否定されると感情を抑えて諦めてしまいます。成長の妨げになるので、危ないからとやめさせるのではなく、親は子どもの挑戦を肯定して見守るのが大切です。
判断は子どもにさせる
子どもの挑戦には、どちらを選ぶのかなどの判断する場面が出てきます。親から見るとすぐに判断できるもことでも、代わりに決めてしまっては子どもの判断力や思考力などの非認知能力は伸ばせません。そのため何かを判断する場面では子どもに任せて、自分で物事を選択する経験をさせましょう。
失敗を経験させる
子どもの挑戦には、時には失敗もあります。失敗すると挫折するのではという思いから、先回りして回避させる人もいますが、非認知能力の向上には逆効果です。子どもは失敗を経験することで試行錯誤して、自分自身で問題を解決する能力を鍛えます。そのため失敗はあたたかく見守り、回避させるのではなく励ましの言葉をかけましょう。
頑張りを褒める
挑戦している子どもには、目的を達成できなくても努力の過程を褒めましょう。子どもは褒められると挑戦する意欲が湧き、さらに努力を重ねて困難な問題にも立ち向かえるようになります。頑張りを見つけたら積極的に褒めて、結果以外の部分もしっかり見ていると伝えることが大切です。
子どもの非認知能力の向上で避けること
子どもの非認知能力の向上で避けることは、以下の3つです。
- 他の人と比較する
- 失敗を責める
- 必要以上に干渉する
それぞれについて解説します。
他の人と比較する
子どもの非認知能力を向上させるためには、他の人と比較するのはやめましょう。他人と比較されると子どもは自信を失い、自己肯定感が下がって挑戦をやめる可能性があります。メンタルにも影響してストレスを与えてしまうので、周りの子どもや兄弟などと比較はせずに、本人の個性を大切にする必要があります。
失敗を責める
子どもの挑戦が上手くいかない場合でも、失敗を責めるのはやめましょう。子どもにとって親の存在は大きく、責められると目標達成に力を入れるのではなく、失敗を回避するのに力を注いでしまいます。大きな目標達成の妨げになるので、失敗は責めるのではなく見守り、あたたかい気持ちで支えるのが大切です。
必要以上に干渉する
子どもの挑戦は親から見るとすぐに達成できるものもあるので、つい口を出してしまったり、すぐに答えを出したりする人もいるでしょう。しかし干渉しすぎると子どもの意欲を削いでしまう可能性があります。過剰な助言は避け、挑戦を見守るのが大切です。
非認知能力を高めて子どもの社会性を養いましょう
非認知能力とは、思考力や判断力などの数値化できない能力です。高めると子どもの社会性が発達して、将来生きていくための力になります。伸ばすためには子どもの挑戦を肯定して、失敗してもあたたかく見守る必要があります。また失敗を責めたり他の人と比較したりすると、子どもの意欲を削いでしまう可能性があるので、絶対にしてはなりません。非認知能力を高めて子どもの社会性を養いましょう。